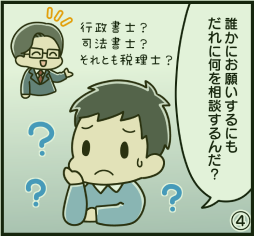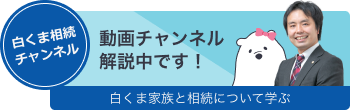相続手続きに関わるようになって約2年、大﨑です。
日々いろんなケースと向き合いながら奮闘しています!
今日は、実際に私が相続手続きに携わる中で
「こんなことをしてるんだ!」と驚いた経験をみなさんに共有したいと思います。
遺言書を書くことに関心がある方はいても、
「見つける側」になることを想像したこと、ありますか??
遺言書の話というと「作る側」の話を聞くことはありますが、
「見つけたとき、どうすればいいのか?」は実はあまり知られていないんです。
言われてみると、たしかにそうだね!
遺言書を見つけたことやその手続をしたことがある人自体、
多くはないんじゃないかな?
そうですよね。
みんなが必ず通る道ではないからこそ、
「まさか自分が?!」となった時にパニックにならないですむよう、
情報共有させていただきます!
手書きで書かれた「自筆の遺言書」や、
公証役場を通していない遺言書を見つけた場合――
実は、家庭裁判所に行く必要があるんです!
その遺言者(書いた方)が亡くなったことを知った相続人は、
『家庭裁判所』にて『検認(けんにん)』という手続きを行う必要があります。
しかも、封がされている遺言書は、
勝手に開けてはいけません!
相続人などの立ち会いのもと、裁判所で開封する決まりになっています。
私自身、はじめて知った時は「えっ、家庭裁判所に行かなきゃいけないの?」
と驚きました。
〝何かトラブルがあったときに行くところ〟というイメージしかなかったので、
遺言書の内容を確認するために家庭裁判所に行くとは思いませんでした。
ふむふむ….
遺言書を発見したときは、
(公正証書による遺言を除いて)家庭裁判所に申請する必要があるってことだね。
ところで「検認」ってなに??
「検認」とは
● 相続人に対して、遺言書の存在と内容を知らせる
● 遺言書の状態(形・訂正・日付・署名など)を明確にする
● 偽造や書き換えを防ぐための手続き
です。
家庭裁判所で検認が終わると、
遺言書と検認したことの証明書がセットになったものを受け取ります。
この「検認」が終わってはじめて、遺言書の内容を実行できるようになります。
(遺言が無効にならないよう作成時の注意は必要です→詳しくは2025/5/24の記事をご覧ください)
なるほど!
誰かが勝手に書き換えたりできないよう、他の相続人に通知したりするためにも
家庭裁判所でチェックを受けるんだね。
補足情報ですが、
遺言を実行する人=「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」といいます。
遺言書に遺言執行者の指定がない場合は、
家庭裁判所に「この人を執行者にしてください」と申請(遺言執行者の選任申立)をすることになります。
士業の方(弁護士など)が執行者になる場合も多いようです。
一つひとつ手順を追って手続を進める必要があるね。
家庭裁判所に行くことは分かった!
で、「検認」を受けるには裁判所に何を持参したらいいの?
基本的には、以下の書類を用意します。
● 遺言書
● 検認(または執行者選任)の申立書
● 遺言者の出生時~死亡時までの戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
● 相続人全員の戸籍謄本
(その他収入印紙や切手なども持参します)
「申立書」は裁判所のホームページに書式があります。
手間がかかりますが、大切な人の想いをきちんと受け取るために必要なステップです。
相続関係の手続をするときは
基本的には戸籍集めは必須だね!!
そうですね。戸籍収集は必須です!
その他、
● 相続財産を放棄するか判断するための期間を延ばしたいとき
● 相続を放棄するとき
こんな時も家庭裁判所に行き、手続を行います。
何かあったときに慌てないよう、
「いざという時は、家庭裁判所に行くケースもあるんだ!」と、
ぜひ心の片隅に置いておいてくださいね。